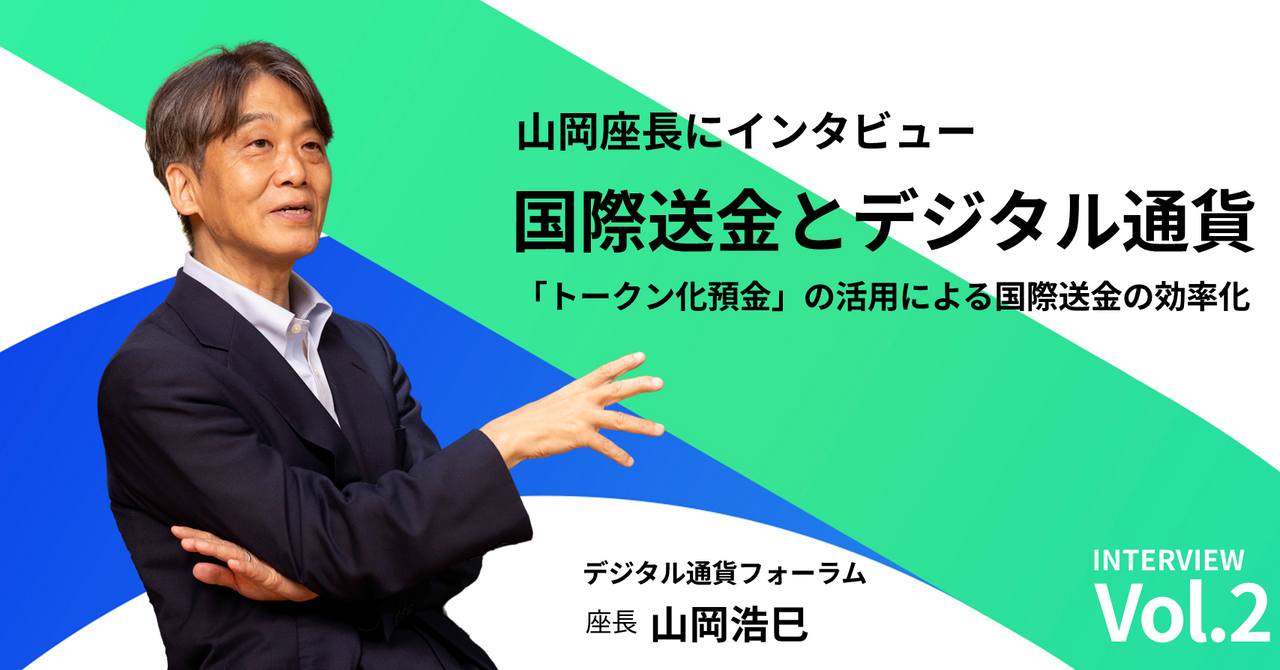
前回は、銀行送金の基本的な仕組みと国際送金の仕組みについて山岡座長に教えていただきました。その中で、国際送金は時間も手間もかかり、この取り組みから撤退する銀行が増えているというお話を伺いました。国際送金から撤退する銀行が増えるとどうなってしまうのでしょうか。このような環境をデジタル通貨によってこの国際送金が変えることができるのか、引き続き山岡座長にお話しを伺いました。
国際送金網の縮小
事務局:「金融包摂」の観点からは大きな問題ですね。
山岡座長:はい。もちろん犯罪やマネロン対策はしっかりやらなければいけない訳ですが、一方で、これらの国々から海外に出て真面目に働いている人々からの本国の家族への送金や、海外の大学で学ぼうとしている人々への送金まで難しくなってしまうことは、深刻な問題です。
2019年に公表された、フェイスブック(当時)が主導した「リブラ計画」も、「国際送金が年々難しくなっている中、誰もが使える低コストの国際送金手段を実現したい」という趣旨を目的に掲げていました。リブラ計画はその後頓挫しましたが、ブロックチェーン・分散台帳技術を使って国際送金を便利にできないかという問題意識はその後も続いていました。
G20も国際送金の効率化を大きなテーマとして掲げています。「ロードマップ」を示して取り組みを続けることを宣言しています。この方針に沿って、金融安定理事会(FSB)は国際送金の改善に向けた「ロードマップ」を作成し、この分野の取り組みの進捗を記述するG20向けの報告書を毎年公表しています。(注)
(注)金融安定理事会による「クロスボーダー送金の改善に向けたG20ロードマップ:2025年統合進捗報告書」
国際送金効率化の取り組み
事務局:具体的にはどのような取り組みが行われているのでしょうか。

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長
山岡座長:比較的早期から、国際送金の指図をなるべくネッティング(差し引き計算)して国内送金に置き換えるビジネスが登場していました。例えば、エジプトからインドに100の送金をしたい人がいる場合、逆方向のインドからエジプトに80送金したい人がいれば、両者をうまくネッティングをすることで国際送金の相当部分を国内送金に置き換え、国際送金はエジプトからインドへの20だけに減らせることになります。このようなネッティングの活用は、とりわけ少額の送金では魅力的です。
ただ、企業間の大口送金などもカバーする抜本的な解決方法としては、やはり新しいデジタル技術であるブロックチェーンおよび分散台帳技術の活用に期待が集まっています。
これらの技術は、「ある一定の条件が満たされたら取引を自動的に執行する」といった「スマートコントラクト」と呼ばれる機能を実現でき、しかもこの機能を1年365日、1日24時間動かすことが可能です。したがって、これらの技術によって、国際送金に関連する口座記録、すなわち、送金銀行や受取銀行の帳簿に加え、コルレス銀行の口座記録や関係する中央銀行当座預金口座の記録を一斉に更新することで、国際送金を効率化できないかが検討されています。
事務局:たいへん夢のある話ですね。ブロックチェーンや分散台帳の支払決済手段への応用としては、トークン化預金のほかにも中央銀行デジタル通貨(CBDC)、ステーブルコインなどがありますが、この中で、国際送金への活用という面での「トークン化預金」の可能性についてはどのように捉えられているのですか。
山岡座長:国際送金への活用という面で、ブロックチェーン・分散台帳技術や「トークン化」を応用する支払決済手段の中で「トークン化預金」は大いに期待されています。
その理由は、先ほど申し上げたように、現在の「コルレス送金」の仕組みでも、中心的な役割を果たしているのは民間銀行であり預金口座であることが挙げられます。しかも、現状のコルレス送金のやり方では、送金のたびに記録を更新しなければいけない口座がたくさんあるため、効率化の余地も大きいと考えられます。
また、資金の受け取り手からみれば、これまで同様、その国の通貨建ての預金としてお金を受け取れることは大きなメリットです。とりわけ企業は、国際送金として受け取ったお金を別の支払いに使いたいわけですから、この点は重要です。
中央銀行の集まりである国際決済銀行(Bank for International Settlements)、通称「BIS」も、「トークン化預金」を使って国際送金を効率化するための実証実験などを積極的に進めています。例えば、2024年に開始された「プロジェクト・アゴラ」は、分散台帳技術を使ったプラットフォーム上に、「トークン化」された預金と中央銀行預金を載せ、安全で効率的なクロスボーダー決済を実現しようというプロジェクトです。
本年6月にBISが公表した「次世代の通貨・金融システム(The next-generation monetary and financial system)」と題する論文でも、かなりの字数を割いて、ブロックチェーン・分散台帳技術や「トークン化」が国際送金を効率化する展望について語っています。
国際送金では民間銀行や中央銀行の多くの口座記録を更新する必要があります。そこで、銀行預金と中央銀行預金の両方を「トークン化」し連携させたうえで、その「プログラマビリティ」、すなわち「プログラム可能な性質」を使って、国際送金を「条件付きの取引」と捉えることで、関連する記録を一斉に更新できないかというものです。
このような一斉更新の姿は「アトミック」と表現されます。
「アトミック」とは、関係する全ての記録が一斉に更新されるか、それとも全てそのままかのどちらかになり、「一部だけ更新される」という状態は決して起こさないことを意味します。これにより、国際送金のコストに加え、リスクも削減できることが期待されています。
もちろん、国際送金では顧客確認(KYC)やマネロン対策(AML/CFT)もしっかり行う必要があります。これに関しては、近年発達の著しい人工知能(AI)をプラットフォームに組み込むことで、疑わしい送金指図を効率的に見つけ出せる可能性を、BIS論文は指摘しています。
事務局:民間レベルでも「トークン化預金」の国際送金への応用は進められているのですか。
山岡座長:いくつかの取り組みが注目を集めています。中でも良く知られているものに、シンガポールのPartior社によるものがあります。
これは、国際送金をブロックチェーン・分散台帳技術とスマートコントラクトで効率化することを目指すもので、JPモルガンやドイツ銀行、スタンダードチャータード銀行やDBSなど世界の主要銀行が協力しているプロジェクトです。
具体的には、これらの銀行が共有できるブロックチェーンベースのプラットフォームを作り、参加銀行間で行われる国際送金について、スマートコントラクトの活用によって関連する記録を一斉に更新することで、国際送金を迅速化し、コストも引き下げることを狙っています。
(参考)㈱ディーカレットDCP 2025年9月16日プレスリリース「SBI新生銀行、Partior、ディーカレットDCPの3社がトークン化預金での外貨取引に関する本格検討開始で合意」
事務局:デジタル技術とデジタル通貨の活用が、国際送金の効率化につながっていくのではないかと期待されている背景が良くわかりましたし、イノベーションとしての意義は大きいですね。

山岡座長:国際送金の課題は、G20でも指摘され続けている世界的な問題ですし、この問題を新しいデジタル技術で解決しようというのは大変夢のある話です。この中で、ネッティングの利用や、ステーブルコインも含めたブロックチェーン・分散台帳技術の活用など、さまざまな取り組みが競われていることは、イノベーションや金融の社会的使命という視点からも望ましいことだと思います。
そのうえで、国際送金においては、送金そのものの安全性や迅速性に加え、金融システム全体の安定性という観点も重要です。国際送金において「コルレス送金」という方法が採られているのも、1974年のヘルシュタット銀行の破綻が示すように、国際送金の過程で一者でも破綻する関係先が出てきては大変であり、だから各国できちんと規制監督され信頼できる銀行だけをコルレス銀行にし、これを繋いでいこうという発想によるものです。
この点、先ほど申し述べた「アトミック」の技術は、リスクのさらなる削減につながるでしょう。 さらに、とりわけ国際送金では、送金が犯罪やマネロンなどの不正行為に使われないようきちんと監視していくことも重要です。 加えて、国際送金の問題は、国際金融システムのあり方にも関わってくる面があります。
極端な話、国際送金が大変なら世界中の人々が一種類の通貨を使い、中央銀行も一つにしてしまってはどうかという話にもなりかねない訳ですが、そうなると現在各国が持っている経済政策の自律性・主体性も失われることになります。この世界にとってどのような通貨体制が望ましいかは、より広い視点から考えなければならないテーマです。
現在の金融インフラの下、民間銀行と中央銀行は互いに協力し、顧客確認やマネロン対策などの機能も果たしながら、企業間の大口送金も含め、国際送金の機能を果たしてきています。このような現存するメリットを活かしながら、ブロックチェーンやトークン化、スマートコントラクトなどの新しい技術を積極的に取り込んで国際送金を効率化していくという点で、「進化型預金」としてのトークン化預金の活用は、大変有望だと思います。
事務局:本日はどうもありがとうございました。
話者紹介

山岡 浩巳
デジタル通貨フォーラム座長
フューチャー株式会社取締役 グループCSO
日本銀行において調査統計局景気分析グループ長、同企画室企画役、同金融機構局参事役大手銀行担当総括、金融市場局長、決済機構局長などを務める。この間、国際通貨基金日本理事代理、バーゼル銀行監督委員会委員なども歴任。

