
トークン化預金であるデジタル通貨DCJPYを使うメリット

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長
さらに、DCJPYは預金として「ファンジブル(fungible)」であり、四則演算が可能であることが大きいと思います。
一方が100円の債権を持ち、もう一方が50円の債権を持っていた場合、100円と50円を相殺して一本の50円の債権にできるというのがネッティングの考え方であり、これが可能であるからお金が幅広く支払決済手段に使えるわけです。これは、お金が抽象的で、足し引きが可能であるからです。
この観点から、私は当初から、暗号資産が支払決済手段に使えるという主張には違和感がありました。例えば、一方が100の暗号資産Aを持ち、他方が50の暗号資産Bを持っていた場合、両方が積みあがっていくのでは効率的な精算にはならないわけです。決済は、両者を差し引いて50にできるから便利なのであって、それができなければ効率化につながらないはずです。
では、皆様から見て、デジタル通貨DCJPYを支払決済インフラとして使うことのメリットや、具体的にどのような分野で有効と考えられるかなどについて、見解を賜れればと思います。
日野氏
支払いというのは、今は銀行振り込みが大多数と思いますが、何か別のものに代替していく時に今お話しのあった暗号資産では対価保証の部分や企業の信頼という形での取引に充当することは難しいように思えます。
DCJPYは暗号資産やステーブルコインとの違いとして、銀行が利用しているブロックチェーン技術の仕組みである、窓口が全て銀行であるというのは企業において大きな信頼であり重要なポイントであると思います。
また、EDIの普及のお話しがあったように、民間企業が自社の効率化と利益のために始めた仕組みというのは、どうしても偏りが出てしまうので公平性という点では課題が出てしまうと思います。つまりメリットがある企業もあればメリットが全くない企業も出てしまいます。
DCJPYは第三者のインフラとして存在ができて、かつ銀行という全体的な信頼を置いている機関が独自役割として果たす仕組みは、企業としても信頼して取引決済手段として使うことができると思います。

株式会社オービックビジネスコンサルタント 日野 和麻呂氏
では、これをどの分野から使われていくかと考えると、ボトムアップというのは難しいのですよね。
小規模企業から大手に使いたいとメッセージは送れないとか、EDIもそうですが1社がやろうと思っても必ず相手がいるものなので、両者が使わないと成立しない話からすると、今のデジタルインボイスの様な話も同じ点がネックでなかなか普及しないという課題が出ています。
こういった状況を考えると、EDIというデジタルでの取引も既に始めている企業、双方デジタル取引をやっている方々が、商流がデジタル化しているので金流もデジタル化でやっていこうという流れが一番スムーズではないかと感じています。
流通EDIが普及されている業界の方々からぜひ活用していただきたいですし、そこから広がっていくのではないかと期待しています。
岩田氏
多くの人は、ブロックチェーン技術を使ったデジタル通貨と言うとビットコインのような暗号資産を思い浮かべると思います。DCJPYの認知や可能性がどこまで広がるかは、利便性を知ってもらうと同時に不安を払拭してもらうことが非常に重要だと思います。 企業の支払い業務における課題は、請求書処理の煩雑さ、支払データの不整合、不正リスクなどがあげられます。
また企業間の決済手数料が高いことも大きな課題の1つです。インターネットバンキングなどでは振込手数料が安くなってきているとはいえ、件数が多ければ多いほどコストは膨大になり、振込エラーが発生する確率も高くなります。
DCJPYはトークン化したデジタル通貨でスマートコントラクトにより、決済の自動化ができるという意味では支払先が多い企業、あるいは一見の取引先が多い業種などには特にメリットがあるのではないでしょうか。
山岡座長
私が日本銀行勤務時代に、組織として欧州中央銀行(ECB)と共同研究の形で中央銀行デジタル通貨の研究を始めたのですが、当時、組織内にはブロックチェーンの技術者はいませんでしたので、出向者の方に来て頂いたり、福田さんのおられる日立製作所など外部の企業の力添えを頂いてきました。
例えば、資金と証券の移転を同時に行うための「アトミック・スワップ」、すなわち、片方だけが受け渡されることのないような仕組みの構築などが、多くの方々の協力の下で進められたことを覚えています。そこで、技術の経験も豊富な福田さんからご覧になって、技術面からDCJPYのようなブロックチェーンベースのプラットフォームを利用するメリットを、どのようにお考えでしょうか。
福田氏
重複した話になるかもしれませんが、ブロックチェーンでなくても良いかもしれないのですが、ブロックチェーンを使って一番簡単に実現できることは耐改ざん性の高いデータとして扱えることと、取引する人たち同士が同じものを見られる透明性です。
そこに付随して色々プログラムを組み込めるという技術が付いてくるのではないでしょうか。
これを両立するための基盤なので、これが実現できるための方法が必ずしもブロックチェーンである必要はないけれども、簡単に実現ができるので、ブロックチェーンでやってしまえばというぐらいに技術的にも知名度も上がってきているのかなと思います。 そこに付随して色々プログラムを組み込めるという技術が付いてくるのではないでしょうか。
今後のインボイスチェーン分科会の活動について
山岡座長
日本では長らく、非製造業の生産性引き上げが課題と言われ続けています。この中で、インボイスチェーン分科会の活動を通じて、オールジャパン的な課題ともいえる、日本の受発注全般の実務やビジネス慣行、小売チェーンの効率化などを進めていく上で、我々としてどのような貢献ができるか、最後にお話を伺えればと思います。
日野氏
この今検討している基盤が社会実装に至って各企業様が使われるステージに行くまで、まだまだ色々な課題があるかと思います。今後、認知度をもって提供されたとすると、どこかの企業が作った独自の基準ではなく標準プラットフォームに成り得る点はとても大きなインパクトがあります。 当社も他のシステムと何か接続をする際は、どうしてもどちらかの仕様に寄せる必要がありいつも議論になります。
しかしインボイスチェーンであれば標準技術でどの企業が使おうとも同じ形で接続し、一度作ったものはずっとそこに繋がり続けられる点は、システムベンダーとして期待が高いインフラになり得ると思います。
今は圧倒的な少子化・人口減が大きな課題となっており、その解決手段にAIが注目されています。AIエージェントのようなものがムーブメントで言われていますが、AIエージェントとはある意味AIが人間を代替することです。この代替により何が起こるかというと、今まで人がシステムの画面を使って入力していたところを、AIがカバーしてくれるのです。
受発注という行為には判断と言う要素が入りつつも、ここで確定した以降の支払いから経理までは実は決まった数字に対する単なる作業だったりします。 イレギュラーやミスのチェックなどはあるけれども、一度納品チェックが終わってしまえば、納品先が支払って入金を確認して売り上げにする流れは、ある意味全てパターン化できますのでこの基盤ができるとAIがほぼ代替する将来が実現可能になってくると思います。
これまでこの業務処理をしていた方々には、もっと付加価値の高い業務へアプローチをしたり、このAIをコントロールしたり管理するような業務に発展する将来像もできると思いますし、その世界を実現するためには、システム間で接続し合うための共通プラットフォームはいずれにしても必要ではないかと思います。 DCJPYネットワーク・インボイスチェーンの基盤には非常に期待ができると感じています。

株式会社 日立製作所 福田 圭氏
福田氏
私が技術面から見るDCJPYの一番の特徴は、プログラマブルであることだと思っています。
先ほどアトミック・スワップのお話を出していただきましたが、単に金銭的なバリューを交換するのではなく、それ以外の情報を併せて交換するなど、ある意味無限の可能性を持っていると思います。そのため、このできることをいかに認知してもらいユーザーにやってもらうかということが、一番大きな課題ではないでしょうか。ここを突破できれば恐らくすごく広がっていく技術だと思っています。
サプライチェーンの最後に決済機能としてDCJPYに繋がるためには、まずはDCJPYそのものの認知度を上げていかなければならないですし、上がっていけば色々なことができる、そうすればプログラマブルの良い面がどんどん出てくるではないでしょうか。どのように底上げしていくかが恐らくこれからの課題かと思います。

株式会社ミロク情報サービス 岩田 悟氏
岩田氏
個人の決済ではここ数年でキャッシュレス化が急速に普及したように、DCJPYも企業間取引の決済手段の1つとして当たり前のように利用される時代がくる、そんなポテンシャルを秘めたものと考えています。
また企業間取引のDXによってバックオフィス業務の効率化、不正防止に繋がっていくことを期待していますし、誰もがメリットやベネフィットを享受できるようにしていくことが一番の理想形だと思います。
最終的にはDCJPYと海外のステーブルコインが連携され、海外取引での決済まで可能になれば、より広がりが持てるでしょう。
山岡座長
先ほどAIというキーワードが出ましたが、生成AIは小売業に対してもインパクトが大きく、実務を大きく変えていくだろうと思います。日本の課題として、どのように産業の生産性を上げるか、多くの方が頭を悩ませているのですが、企業間精算業務においても、単なるペーパーレスではなく、生成AIなどの新たな技術も応用しながら仕事のやり方全体を変えていくことが課題になると思いますし、それができれば大きな生産性の向上に結びついていくように思います。
この中で、プログラマブルなマネーとして、条件付きの支払指図など組み込むことができる支払決済手段は、資金流として重要な役割を果たせるものだと思います。また、そのためには産業を超えた連携が必要とも思います。
このような取り組みを進めていく上でも、インボイスチェーン分科会の活動の意義は非常に大きいと思います。この分科会の活動が、日本の産業全体の生産性向上に結びついていくことを強く期待しております。
本日はありがとうございました。

話者紹介

山岡 浩巳
デジタル通貨フォーラム座長
フューチャー株式会社取締役 グループCSO
日本銀行において調査統計局景気分析グループ長、同企画室企画役、同金融機構局参事役大手銀行担当総括、金融市場局長、決済機構局長などを務める。この間、国際通貨基金日本理事代理、バーゼル銀行監督委員会委員なども歴任。
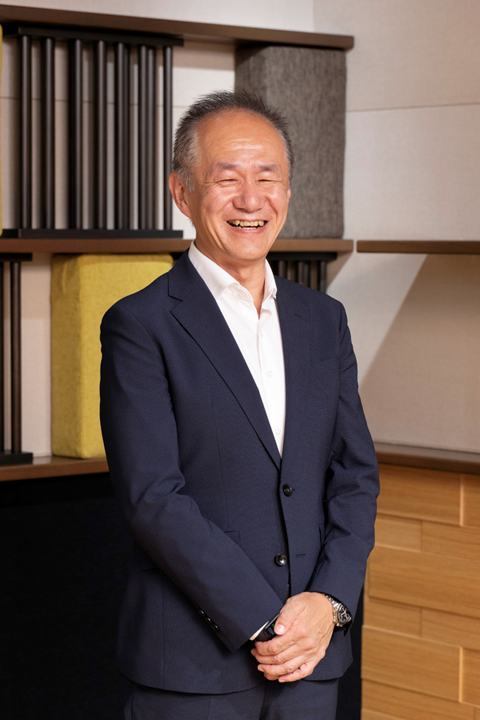
日野 和麻呂
株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)
執行役員 開発本部 ICTセンター
部長
デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会幹事。
1989年株式会社オービックビジネスコンサルタントに入社。営業や販売推進を経て、現在は開発本部ICTセンター部長として、クラウドサービス運用における品質確保や監視体制構築に従事。ソフトウェア協会(SAJ)の推薦を受け、情報処理推進機構(IPA)の「ソフトウェアモダナイゼーション委員会」委員として、標準化・DX推進にも取り組む。
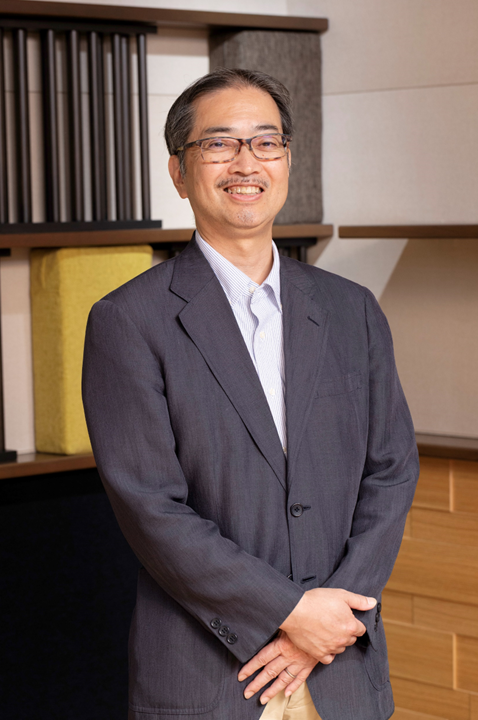
福田 圭
株式会社 日立製作所
マネージド&プラットフォームサービス事業部
サプライチェーンマネージメントサービス本部 ブロックチェーン・Web3推進部
部長
デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会幹事。
システムエンジニアとして、バンキングシステムやサプライチェーンシステムなど、様々な業務システムの構築・運用に関与。 日立アメリカや日立中国で、海外の最先端システム調査やソリューション企画業務にも従事。 2018年にブロックチェーン推進部を立ち上げ、現在はブロックチェーン関連ソリューションの規格及び提供に携わる。

岩田 悟
株式会社ミロク情報サービス 営業本部
DX事業戦略室 DX事業グループ
参与
デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会幹事。
長年開発部門において会計事務所向けおよび一般企業向けERPの開発および製品企画に従事。 その後クラウド推進部、新規事業戦略室などで新規事業のプロジェクト立ち上げに携わる。 現在はDX事業戦略部において中小企業のDX化を支援。



山岡座長
支払決済インフラとして、トークン化預金であるデジタル通貨DCJPYを使うメリットとして、まずDCJPYが「預金」であることが大きなメリットだと思います。 例えば、インボイスを使って色々な受発注を行う場合、企業のバランスシート上では、さまざまな債権債務関係が解消される都度、バランスシートから消し込んでいくことになります。
逆に、支払決済のたびに、暗号資産やステーブルコインなどの新たなアセットがバランスシートに乗ることになると、効率化になりません。
また、企業にとって、決済手段の価値が安定していることはとても重要です。1万円の財やサービスの対価として受け取ったものの価値は1万円でなくてはいけない。9,999円ではダメなのです。この支払手段は受け取れませんとか、足りない1円分を何か他のもので払ってくださいとなると混乱につながります。額面1万円の決済手段は、究極的には1万円の現金と交換できなければいけないという支払決済手段の要件は「シングルネスオブマネー(Singleness of money)」と呼ばれますが、DCJPYは、既に企業間の大口決済に広く使われている預金として設計され、価値が安定し、会計上も預金として計上できることは大きいと思います。