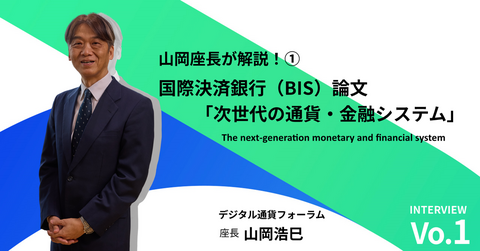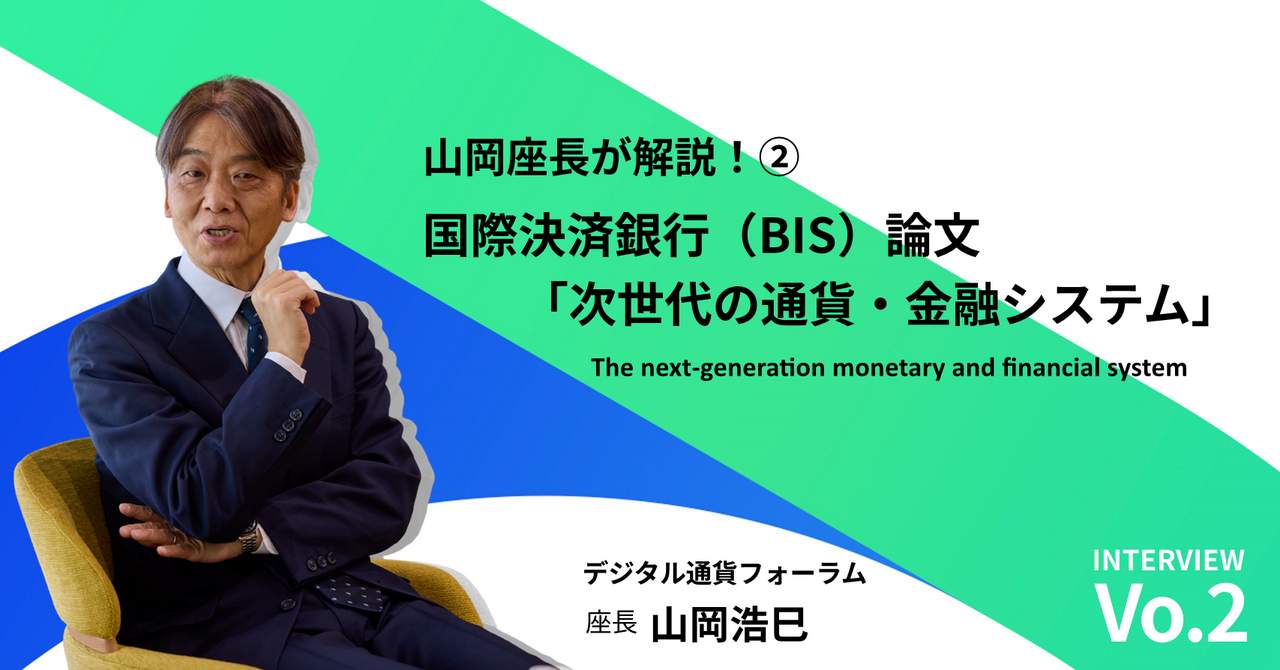
第1回では、「中央銀行の中央銀行」とも言われる国際決済銀行(BIS)がどのような機関であるのかを中心に2025年6月に公表した論文(年次報告書:「次世代の通貨・金融システム」)について山岡座長に触れていただきました。第2回からは、この論文で示されたこれからの支払決済手段に求められる要件「単一性(singleness)」「弾力性(elasticity)」「健全性(integrity)」の3点について詳しく解説いただきます。

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長
デジタル通貨フォーラム事務局(以下、事務局):それぞれの内容を説明して頂けますか?まず「単一性」とは何でしょうか?
山岡 浩巳座長(以下、山岡):「単一性」とは、例えば「円」など同一の通貨単位で表される支払決済手段は、現金であろうと預金であろうとモバイル決済であろうと、常に額面通りの価値を持ち、互いに、完全に1対1(at par)で交換できなければいけないということです。
例えば、「100円」と表記されている支払決済手段は、常に100円の支払いに使えなければなりません。このような信頼が社会に共有されていることが、通貨システムの礎であると、この論文は説明しています。
もしも、「100円」と表記されている支払決済手段が、受取側にとって99円の価値しかないと捉えられれば、受取側は「その支払手段は受け取れません。他の手段で払ってください」と言うでしょう。そうなると、通貨システムの中に「使える手段」と「使えない手段」が混在することになります。さらに、いずれ支払いに使えると信じて持っていた支払決済手段が、ある日突然使えなくなる事態になりかねません。そうなると、社会は大混乱に陥ります。
事務局:通貨の「単一性」の重要さは、本当にその通りですね。では、この要件を満たす上で、トークン化預金とトークン化中央銀行預金の組み合わせが提唱されているのはなぜでしょうか。
山岡:この文は、中央銀行と民間銀行からなる、現状の「二層型」の通貨システムの優位性を丁寧に解説しています。
この仕組みのもと、中央銀行は中央銀行預金を民間銀行に提供し、民間銀行は預金を個人や企業に提供しています。民間銀行の間にはもちろんある程度の信用力の差が生じ得るわけですが、どの銀行が発行する預金であっても、100円の預金は100円の支払いに使え、100円の現金と交換できます。これは、支払決済手段としての預金が自己資本規制などの銀行規制や預金保険、さらには中央銀行による「最後の貸し手」(LLR)機能などによって守られているからです。
その上でこの論文は、「トークン化中央銀行預金とトークン化預金の組み合わせ」は、このような二層型通貨システムの構造とその長所をそのまま活かせると述べています
事務局:「トークン化預金」の利点については、既にデジタル通貨フォーラムでも調査研究を重ね、対外的にも説明していますね。では、この論文が「トークン化中央銀行預金」に求めている役割についても教えてください。
山岡:この論文は、預金も含め、さまざまな支払決済手段が「単一性」を維持できるのは、究極的には「アンカー」としての中央銀行の債務につながっているからだと解説しています。民間銀行は中央銀行に口座を持ち、自らの債務を中央銀行の債務である銀行券や中央銀行預金と常に一対一で交換できます。また、例えばモバイル決済手段は銀行預金とつながっていて、これを経由する形で、やはり中央銀行の債務と間接的につながっています。
事務局:では、民間銀行の預金だけでなく中央銀行の預金もデジタルトークン化することの意義は何なのでしょうか?
山岡:この論文、次世代の通貨・金融システムでは、「プログラマビリティ」、すなわち支払決済手段の中にプログラムを組み込めるようにし、さまざまな「帳簿」 ― 実際には電子的な記録ですが ― が連動しながら更新される姿を想定しています。
この中で、「プログラマビリティ」を備えたトークン化預金の帳簿の更新と連動してトークン化中央銀行預金の帳簿も更新することで、さまざまな取引が瞬時に、かつ、アトミック決済 ―取引の全部が遂行されるか全て遂行されないかのどちらかであり、一部だけが遂行されることはない― の仕組みを通じて安全に行われることが展望されています。
事務局:では、次の要件である、通貨にとっての「弾力性(elasticity)」の意義はどのように説明されていますか?
山岡:支払決済手段へのニーズは、取引量などに応じて日々変動します。例えば、経済が成長し取引が活発になれば、それだけ多くの支払決済手段が必要となります。 これとの関連でも、この論文は現在の二層型通貨システムの長所を丁寧に説明しています。
例えば、企業が成長し、より大きな取引や投資を行うようになると、より多くのお金を銀行から借り入れようとします。銀行はそうした借入需要が妥当か、また、過度なリスクがないかどうかなどを自ら判断し、与信に応じるかどうかを決めます。このように、銀行という民間経済主体の自律的な判断を経由しながら、信用創造を通じて預金通貨の供給を増やせるわけです。
このように、経済成長などに応じて必要となる通貨の量を弾力的に供給できるかどうかも通貨システムの重要な要件だと、この論文は説明しています。
事務局:この観点からも、トークン化預金とトークン化中央銀行預金の組み合わせが望ましいということなのですね。
山岡:そうです。部分準備制度のもと、今の通貨システムの仕組みをそのまま維持する形で、銀行システムはトークン化預金の供給を弾力的に増やすことができます。これも、この論文がトークン化預金とトークン化中央銀行預金の組み合わせを推奨している大きな理由です。
事務局:では、通貨の「健全性(integrity)」の意義はいかがでしょうか?
山岡:このintegrityという言葉は、キリスト教の盛んな国々からのレポートには頻繁に使われるのですが、なかなか日本語に訳しにくいですね。敢えて言えば、「一体のものとして正しく、信頼されている」という感じでしょうか。この論文では、integrityは「犯罪や不正取引、マネロンなどに使われないような仕組みがある」という意味で使われていますので、日本語では「健全性」に近いかと思います。経済社会の中核を担うべき支払決済手段が、犯罪や不正取引、マネロンなどに使われやすいものであっては困るという問題意識です。
現在の通貨システムでは、預金口座を提供する銀行が顧客確認(KYC)やマネロン対策(AML/CFT)を行っています。トークン化預金も、基本的に銀行の口座を経由して提供されることになりますので、現在のKYCやAML/CFTの枠組みをそのまま維持できることになります。